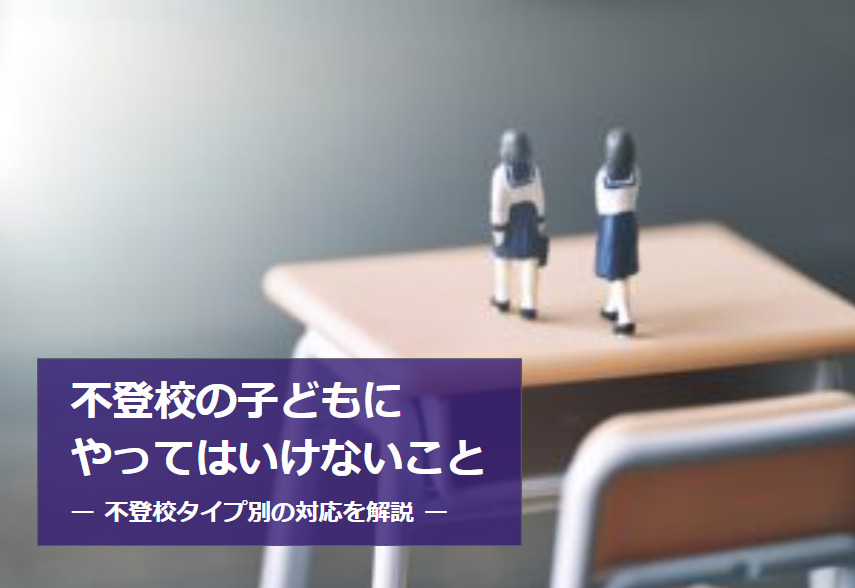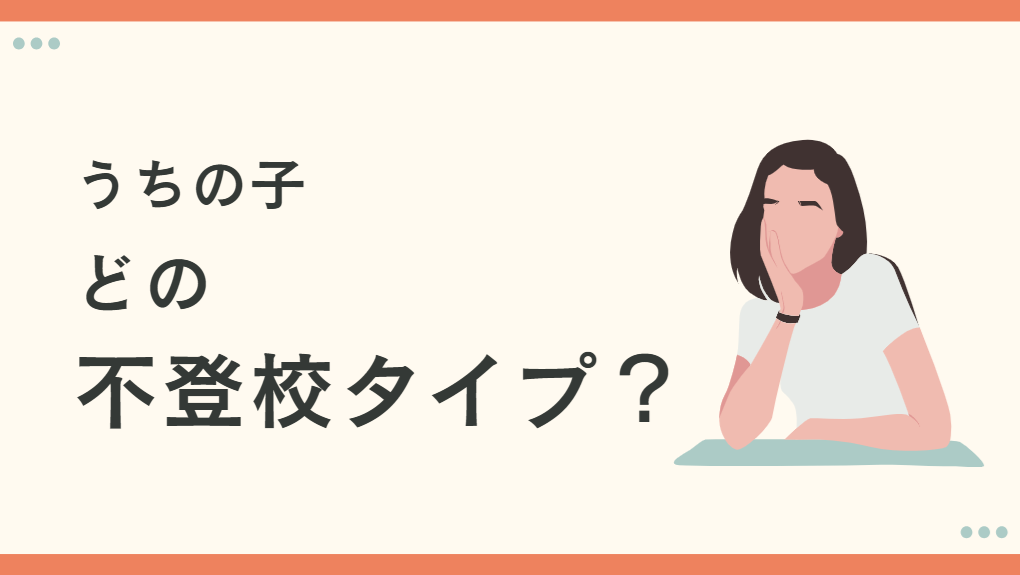「子どもが学校に行きたがらない」
「子どもとどう接すればいいのかわからない」
お子さんの不登校に直面したとき、保護者の多くが戸惑い、不安を抱えることでしょう。
「学校に行かないことは甘えではないか」「育て方が悪かったのでは」とお子さんや自分を責めてしまう方もいるかもしれません。
しかし、不登校の背景には、友人関係の悩み、勉強のストレス、先生との相性、家庭環境の変化、体調不良など、さまざまな要因が絡み合っています。
保護者ができることは、お子さんや自分自身を責めるのではなく、「どうしたら今の状況を少しでも良くできるか」を一緒に考えていくことです。
本記事では、不登校の主な理由や、保護者が取るべき具体的な対応策を年齢別に解説し、避けるべきNG行動や、不登校から回復するためのステップについて詳しくご紹介します。
また、保護者が相談できる支援機関についても触れ、ひとりで抱え込まないためのサポート体制についてもご紹介します。
不登校は決して「人生の終わり」ではなく、お子さんが自分らしく生きる道を模索する大切な過程でもあります。
焦らず、親子で一緒に前を向いて歩んでいくためのヒントを、ぜひこの記事から見つけてください。
不登校の原因は親じゃない
お子さんが学校に行けなくなったとき、「自分の育て方が悪かったのではないか」と自責の念に駆られる保護者は少なくありません。しかし、結論から言えば、不登校の原因は必ずしも保護者のせいではありません。
文部科学省の調査によると、不登校の理由として多いのは「友人関係のトラブル」「勉強のプレッシャー」「先生との相性」「学校の雰囲気が合わない」など、学校生活におけるストレスが大きく影響していることがわかっています。
また、繊細な性格や発達の特性、家庭環境の変化(引っ越しや親の離婚など)、体調不良など、さまざまな要因が絡み合っていることもあります。
もちろん、家庭環境がお子さんに影響を与えることはありますが、それは決して保護者の責任とは限りません。
お子さんが「学校に行けない」と感じる背景には、その子自身の感じ方や性格、外部の環境が関係していることが多く、保護者がどんなに愛情をもって接していても起こりうることなのです。
保護者がすべきことは「責める」のではなく「寄り添う」こと
「親のせいかもしれない」と考えると、つい焦って「なんとかしなければ」と行動してしまいがちです。
しかし、不登校の子どもにとって一番大切なのは、安心できる居場所があること。 それが「家」であり、「親の存在」です。
まずは、「学校に行けなくなったことは悪いことではない」「あなたのことを大切に思っているよ」と伝え、お子さんの気持ちに寄り添いましょう。保護者が冷静でいることで、お子さんも安心し、自分の気持ちを少しずつ話せるようになります。
不登校の主な理由は?
お子さんが学校に行きたくなくなる理由は、一人ひとり異なります。
不登校の背景には、学校でのストレス、家庭の環境変化、心や体の不調 など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。ここでは、不登校の主な理由について詳しく見ていきましょう。
① いじめや友人関係のトラブル
不登校の理由として最も多いのが友人関係の悩みです。いじめや仲間外れ、トラブルが原因で「学校に行くのが怖い」と感じるお子さんは少なくありません。
また、はっきりとしたいじめがなくても、「友達とうまく話せない」「グループに馴染めない」といった孤独感から、学校が苦痛になってしまうこともあります。
② 学業のプレッシャーや学習の遅れ
勉強についていけないことがストレスになり、不登校につながるケースもあります。テストや成績へのプレッシャー、宿題の負担、授業内容が理解できないことなどが学校への不安を増幅させることがあります。
逆に、授業が簡単すぎて退屈に感じる場合も、不登校の原因になることがあります。
③ 先生との相性や学校の雰囲気
担任の先生や他の教職員と合わないことが、学校に行きたくない理由になることもあります。厳しすぎる指導、理不尽なルール、過度な指導によるプレッシャーなどが、お子さんの心に負担をかけることがあります。
また、学校の雰囲気や校則が合わず、息苦しさを感じてしまうことも不登校につながります。
④ 心の不調(精神的ストレス・発達特性)
強いストレスや不安、うつの症状など、お子さん自身の心の不調が不登校の原因になることもあります。また、HSP(繊細な気質)や発達特性(ADHD、ASDなど)を持つお子さんは、学校の環境が合わず、強いストレスを感じることがあります。
⑤ 家庭環境の変化やストレス
引っ越し、親の離婚、家族の不和など、家庭環境の変化もお子さんにとって大きなストレスになります。家の中が不安定だと、安心して学校生活を送ることが難しくなり、不登校につながることがあります。
不登校の理由は一つではない
不登校は、単純に「〇〇が原因」と言い切れるものではなく、いくつもの要因が複雑に絡み合っていることが多いです。そのため、お子さんが「なぜ行けないのか」を無理に決めつけず、まずはじっくり話を聞き、心の負担を減らしてあげることが大切です。
不登校の小学生の親が取るべき5つの対応
小学生の不登校は、環境の変化や人間関係のトラブル、学習のつまずきなどが原因となることが多いです。
特に、入学や進級のタイミングで学校に馴染めず、不登校になってしまうケースもあります。
保護者は、お子さんの気持ちを尊重しながら、安心して過ごせる環境を整えることが大切です。
① 無理に登校を促さず、気持ちに寄り添う
「どうして行きたくないの?」と問い詰めたり、「頑張って行こう!」と励ましたりするのは逆効果になることがあります。
お子さんは言葉で自分の気持ちをうまく伝えられないことが多いため、まずは「学校に行くのがつらいんだね」と共感し、安心できる環境を作りましょう。
② 学校の先生と相談し、柔軟な対応を考える
担任の先生やスクールカウンセラーと連携し、別室登校や短時間登校など、お子さんに合った方法を模索しましょう。学校が苦手なお子さんでも、保健室や図書室なら安心して過ごせることもあります。
③ 家庭で学びの環境を作る
学校に行けない期間も、学習習慣が途切れないように工夫しましょう。
無理に勉強させるのではなく、お子さんが興味を持つことから始めるのがおすすめです。タブレット学習や動画教材を活用し、楽しく学べる環境を整えましょう。
④ 生活リズムを整える
学校に行かない日が続くと、生活リズムが乱れやすくなります。朝は決まった時間に起き、昼夜逆転を防ぐようにしましょう。
適度な運動や日光を浴びることも、心の安定につながります。
⑤ 子どもが安心できる居場所を作る
家の中だけでなく、放課後デイサービスやフリースクールなど、学校以外の居場所を探してみるのも良い方法です。保護者が焦らず見守ることで、お子さんが自分のペースで前向きな気持ちを取り戻せるようになります。
不登校の中学生の親が取るべき5つの対応
中学生の不登校は、思春期特有の悩みや、成績へのプレッシャー、人間関係のトラブルなどが関係していることが多いです。
学校への適応が難しくなる時期だからこそ、保護者はお子さんの変化を敏感に察知し、適切にサポートすることが重要です。
① お子さんの話をじっくり聞く
中学生になると、保護者に本音を話しづらくなることがあります。
しかし、無理に聞き出そうとすると逆効果です。焦らず、お子さんが話しやすい雰囲気を作ることが大切です。
何気ない会話の中で、「最近どう?」と聞いたり、一緒に好きなことを楽しんだりしながら、少しずつ気持ちを引き出しましょう。
② 「学校に行かせること」よりも「心の回復」を優先する
「みんな学校に行っているのに、なぜ行けないの?」と責めたり、無理に学校に連れて行こうとすると、お子さんはさらに追い詰められてしまいます。
不登校の期間は、お子さんにとって「心を休める時間」ともいえます。まずは焦らず、お子さんのペースで回復を見守ることが大切です。
③ 学校やスクールカウンセラーと連携する
担任の先生やスクールカウンセラーと連絡を取り、お子さんが安心して学校に戻れる環境を整えることも重要です。
教室が難しい場合は、別室登校や保健室登校の選択肢を検討しましょう。
④ 家の中で「社会とのつながり」を持たせる
学校に行かない間も、社会とつながる機会を作ることが大切です。
オンライン学習や習い事、地域のボランティア活動など、子どもが興味を持てる活動を一緒に探してみましょう。
⑤ 進学や将来の選択肢を一緒に考える
中学生は、高校受験や将来の進路を考え始める時期です。
もし学校復帰が難しい場合でも、通信制高校やフリースクールなど、さまざまな選択肢があることを伝え、お子さんが自信を持てるようにサポートしましょう。
不登校の高校生の親が取るべき5つの対応
高校生の不登校は、学業のプレッシャーや進路の悩み、人間関係のトラブルなど、さまざまな要因が関係しています。思春期のお子さんは自立心が芽生えているため、親の接し方が非常に重要になります。
①「学校に行く・行かない」の二択ではなく、柔軟な選択肢を考える
高校生になると、学校復帰が難しくなるケースもあります。しかし、「高校を辞めたら将来がない」と悲観せず、さまざまな選択肢を考えることが大切です。
通信制高校や定時制高校、高卒認定試験など、お子さんに合った進路を一緒に検討しましょう。
② 子どもの意思を尊重し、押しつけない
高校生になると、自分の考えをしっかり持ち始めます。
そのため、「こうしなさい」と指示するのではなく、お子さんが自分で選択できるようにサポートすることが大切です。
「どうしたい?」「どんなことに興味がある?」と問いかけ、一緒に将来を考えていきましょう。
③ 自信を取り戻せる環境を作る
不登校が長引くと、自分に自信を失ってしまうことが多くあります。
アルバイトや趣味の活動など、学校以外での成功体験を積めるような環境を整えましょう。小さな成功体験の積み重ねが、自己肯定感の向上につながります。
④ 専門機関のサポートを活用する
不登校が続き、お子さんの様子に変化が見られる場合は、カウンセリングを受けることも選択肢の一つです。
高校生になると、保護者には相談しづらいことも増えるため、信頼できる第三者の存在が重要になります。
⑤ 焦らず、長い目で見守る
高校生の不登校は、進路に直結するため、保護者も不安を抱えがちです。
しかし、「今の状況がずっと続くわけではない」と考え、お子さんの成長を長い目で見守ることが大切です。
お子さんが自分で道を選び、前向きに進めるようにサポートしていきましょう。
親がやってはいけないこと
お子さんが不登校になると、保護者としては「どうにかして学校に戻してあげたい」と焦る気持ちになるものです。
しかし、保護者の対応次第では、お子さんがさらに追い詰められてしまうこともあります。
ここでは、不登校のお子さんに対して保護者がやってはいけない行動について解説します。
① 無理やり登校させようとする
「明日は絶対に学校に行きなさい」「休んでばかりじゃダメ」といった言葉で無理に登校を促すのは、お子さんにとって大きなプレッシャーになります。
特に、不登校になり始めたばかりの時期は、学校に対する恐怖心や不安が強くなっていることが多いため、無理に登校させることでさらに状況が悪化する可能性があります。
まずは「学校がつらいんだね」「今は休んでも大丈夫だよ」と、お子さんの気持ちを受け止めてあげましょう。
② 不登校を責める・否定する
「なんで学校に行かないの?」「怠けているだけじゃないの?」と責めたり、「みんな頑張ってるのに」「親として恥ずかしい」と否定したりするのは絶対に避けるべきです。
不登校になったお子さん自身も、「このままでいいのかな?」という不安を感じていることが多いです。そこに保護者からの否定的な言葉が加わると、「自分はダメな人間だ」と自己肯定感が低くなり、ますます動けなくなってしまいます。
③ きょうだいと比較する・他の子と比べる
「お兄ちゃんはちゃんと学校に行っていたのに」「○○ちゃんは休まず通ってるよ」と他のお子さんと比較することで、不登校のお子さんは強い劣等感を抱くことになります。
きょうだいや同級生と比べるのではなく、「今の自分にできることは何か?」を一緒に考える姿勢が大切です。保護者は「あなたはあなたのペースでいいんだよ」と伝え、お子さん自身の成長を大切にしてあげましょう。
④ 不登校を親の責任だと考えすぎる
「私の育て方が悪かったのかも」「もっと厳しくすればよかったのでは?」など、保護者が自分を責めすぎるのもNGです。
不登校の原因はさまざまであり、必ずしも保護者の育て方や接し方が原因とは限りません。保護者が落ち込んでしまうと、その雰囲気を察したお子さんも「自分のせいで親が苦しんでいる」と罪悪感を抱き、余計に追い詰められてしまいます。
「今の状況をどう乗り越えていくか?」を前向きに考えることが大切です。
⑤ 何も対策をしない・放置する
「そのうち行く気になるだろう」と何もせず放置するのも良くありません。
確かに、お子さんが自分から動き出すタイミングを待つことも大切ですが、保護者としてできることはあります。たとえば、お子さんが安心して話せる環境を作る、学校や専門機関と相談する、家庭でできる学習環境を整えるなど、少しずつサポートしていきましょう。
⑥ 自分の価値観を押しつける
「学校は行くもの」「勉強しないと将来困る」など、保護者の価値観を押しつけすぎると、お子さんは苦しんでしまいます。
現代では、学校以外にも学べる場所や進路の選択肢が増えています。通信制高校やフリースクール、オンライン学習など、お子さんに合った方法を一緒に探してみましょう。
不登校を乗り越えるためのステップ
不登校は決して「終わり」ではなく、「新たな道を見つける過程」です。
焦らず、一歩ずつお子さんが前向きに歩めるようにサポートしていくことが大切です。ここでは、不登校を乗り越えるためのステップを紹介します。
ステップ① まずはお子さんの気持ちを受け止める
不登校になったお子さんは、「学校に行かなければならない」と思いつつも、行けない自分を責めていることが多いです。親が「どうして学校に行かないの?」と問い詰めるのではなく、まずはお子さんの気持ちを受け止めることが大切です。
✔ 「つらかったね」「今は休んでも大丈夫だよ」 と声をかける
✔ 安心して話せる環境をつくる(無理に聞き出さない)
ステップ② 休息期間を認める
学校に行けなくなったお子さんは、心身ともに疲れていることが多いため、しばらくの間は無理に登校を促さず、安心して休める環境を整えましょう。
この期間は、お子さんが自分の気持ちを整理する時間でもあります。親が「いつまで休むの?」と急かしてしまうと、かえってプレッシャーになり、不登校が長引くこともあります。
✔ まずは十分に休ませることを大切にする
✔ 子どもが興味を持っていることに触れさせる(読書、ゲーム、趣味など)
✔ 家族との時間を大切にし、安心できる環境をつくる
ステップ③ 学校以外の選択肢を知る
「学校に行かない=将来が閉ざされる」というわけではありません。現代では、学校以外にもさまざまな学びの場や進路があります。
保護者が「学校に戻ることだけが解決策ではない」と理解しておくことで、お子さんにとってより良い道を一緒に考えることができます。
✔ フリースクールや適応指導教室(学校外の学習・交流の場)
✔ 通信制・オンラインスクール(自分のペースで学べる)
✔ ホームスクーリング(保護者がサポートしながら学ぶ)
ステップ④ 学校と相談し、登校のハードルを下げる
お子さんが少しずつ前向きになってきたら、学校と相談しながら、無理のない範囲で学校との関わりを持つ方法を探しましょう。
お子さんの気持ちを尊重しながら、「学校に戻るならどういう形がいいか?」を一緒に考えることが大切です。
✔ 保健室登校・別室登校(まずは学校に行くだけでもOK)
✔ 授業の一部だけ参加する(好きな教科や短時間から始める)
✔ 先生や友達と連絡を取る(学校への不安を少しずつ和らげる)
ステップ⑤ 社会とのつながりを持つ
不登校が長期化すると、お子さんは「自分は社会から孤立している」と感じてしまうことがあります。そのため、学校以外での人との関わりを増やすことも重要です。
学校以外の場でも「自分の居場所がある」と感じられることで、自信を取り戻していきます。
✔ 地域のイベントやボランティアに参加する
✔ 保護者が外の世界を見せる(旅行・アウトドア・習い事など)
✔ オンラインの学習コミュニティや趣味のグループに参加する
ステップ⑥ 子ども自身が「次の一歩」を決める
最終的には、お子さん自身が「どうしたいか?」を決めることが大切です。
保護者が「そろそろ学校に戻ろう」と促すよりも、お子さんが「そろそろ何かしたいな」と思えるような環境を整えることが重要です。
お子さんが「少しずつでも動いてみよう」と思えたときが、次のステップに進むチャンスです。
✔ 「どんな形で学びたい?」と子どもと一緒に考える
✔ 小さな成功体験を積み重ねる(オンライン授業、趣味の活動など)
✔ 焦らず、子どもが動き出すタイミングを見守る
不登校を乗り越える道のりは、一人ひとり違います。大切なのは、お子さんの気持ちを尊重しながら、その子に合ったペースで進んでいくことです。保護者もお子さんも、「今の状況がずっと続くわけではない」と前向きに考え、焦らずに向き合っていきましょう。
不登校の子どもを持つ親の相談先と支援機関
不登校のお子さんを支える親にとって、一人で悩みを抱え込むのは大きな負担になります。
適切な相談先や支援機関を活用することが重要です。不登校への対応に慣れている専門家や団体とつながることで、保護者自身の不安も和らぎ、お子さんにとっても最適なサポートが見えてきます。
不登校のお子さんを持つ保護者が相談できる主な窓口や支援機関を紹介します。
① 学校の相談窓口を活用する
担任の先生やスクールカウンセラーに相談する
まずは学校の先生やスクールカウンセラーに相談することが大切です。
不登校の原因やお子さんの様子を共有することで、学校側と連携しながら支援策を考えることができます。
特に、スクールカウンセラーは、心理的な側面からお子さんをサポートする専門家です。お子さん自身が話しづらいことでも、カウンセラーを通じて本音を引き出せることがあります。
② フリースクールや適応指導教室を活用する
フリースクール
フリースクールは、学校に行けないお子さんが安心して学び、過ごせる場所です。授業のスタイルが自由で、自分のペースで学ぶことができます。また、学校と違った環境で新しい人間関係を築けるメリットもあります。
適応指導教室(教育支援センター)
自治体が運営する施設で、不登校のお子さんが少しずつ学校生活に慣れるための支援を行う場です。個別の学習支援やグループ活動が用意されており、登校に向けた準備ができます。
③児童精神科・心療内科
お子さんが極端に気分が落ち込んでいたり、ストレスによる体調不良が続いていたりする場合は、専門医の診察を受けることも選択肢の一つです。
④ 電話相談やオンライン相談を活用する
直接相談に行くのが難しい場合は、電話やオンラインで相談できる窓口もあります。
✔ 24時間子どもSOSダイヤル(0120-0-78310)(文部科学省が運営)
✔ チャイルドライン(0120-99-7777)(子ども向けの電話相談)
✔ こころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)(メンタルヘルス相談)
これらの窓口では、不登校に関する悩みだけでなく、親自身のストレスや不安についても相談できます。
そのほかの相談先
・教育相談室・教育センター(不登校の対応や復学支援についての相談)
・教育委員会の「教育相談窓口」
・市区町村の「子ども・家庭相談室」
・学校の「スクールソーシャルワーカー」
・全国不登校支援センター(不登校のお子さん向けの学習支援・進路相談)
・NPO法人登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク(親の相談・支援)
・親の会(ピアサポートグループ)
・文部科学省「子どもと親のサポート体制」(公的機関の支援情報)
・NPO法人「登校拒否・不登校を考える親の会」(親同士の交流・情報交換)
・子ども家庭支援センター(親の精神的ケアや子育て相談)
・児童相談所・子ども家庭支援センター
・児童相談所相談専用ダイヤル(189)(子どもの心理相談・虐待相談)
・精神保健福祉センター(子どものメンタルケア・相談支援)
保護者が「頼れる場所がある」と感じることは、お子さんを支えるための大きな力になります。状況に合わせて、適切な相談先を選び、無理せず不登校と向き合っていきましょう。
【まとめ】

今回は、不登校のお子さんのために保護者の方ができる対応ややってはいけないことについてご紹介しました。
お子さんが不登校になった場合、多くの保護者の方は不安や焦りなどの感情を抱くと思います。それは決しておかしなことではありません。しかし、保護者が余裕をなくして疲弊している様子を目にすると、お子さん自身も罪悪感などを感じてしまうかもしれません。
文部科学省が「不登校は問題行動ではない」と表明しているように、不登校への向き合い方も変化が見られており、不登校のお子さんの選択肢も多様性が出てきています。
「フリースクールなど他の手段も沢山ある」「元の学校に戻るだけが選択肢ではない」とわかるだけでも、心が軽くなるかもしれません。それは保護者の方も同様です。保護者も先々にどんな選択肢があるのかわからなくて不安になっているようなことも少なくありません。
不登校のお子さんの進路については、以前よりもたくさんの選択肢が出てきていますので、まずは一度落ち着いて情報を集めてみること、そして、お子さんが安心できる環境づくりから始めてみてはいかがでしょうか。
ツナグバでは、無料で利用可能なQ&A機能がございます。
会員登録のみで、匿名でお悩みなどを発信することができ、専門家からの返事をもらうこともできます。
不登校について何かお悩みのある方は、是非利用してみてください。
▶ ツナグバ Q&Aはこちら
【監修のコメント】
不登校のお子さんへの関わりについて、万人共通の解決方法があるわけではありません。
お子さんの不登校について、抱えている状況も一人一人異なりますし、親子の関係性も異なります。
また、保護者の方の不登校への考え方なども異なりますし、色々な要因を個別に検討していくことが重要になります。
そうした個々の要因や環境などの情報を集めて、個別に見立てて検討していく作業を専門家はアセスメントと呼んでいます。このアセスメントを踏まえて、お子さんや保護者の方にどのように関わっていくのがよさそうかなどを検討しているのです。
しかし、状況は違えども、保護者の考え方や関わり方などがお子さんに与える影響が大きいことは共通であることが多いように思います。
もちろん、学校において明確にいじめがあるような場合や、保護者からの協力がそもそも得られないような場合は、少し違ってくるところもあります。
不登校への対処を考えるときには、お子さんをどうするかということに焦点があたりがちですが、
保護者の方のお子さんへの関わり方が変わると、お子さんも変化を見せてくることは少なくありません。
まずは、お子さんへの関わり方や不登校への認識などを見直してみることも少し考えてみてください。とは言っても、保護者の方自身も余裕がないことや、不登校の本やサイトに書いてある「親はこうすべし」という文言に疲れてしまっている方も少なくはないと思います。
しかし、保護者の方とお話をしていると、余裕がなくてお子さんとの衝突が多い時は「そんなこと言われても、できるんだったら苦労しない」と思っていたけど、後々になるとだんだんその意味がわかってくる、とお話しされる方も少なくありません。
少しずつ変化を見せていく場合も多いですし、一歩進んで二歩下がるような場合もあります。そういう少しずつのしんどさや進展を一人で抱えていると結構しんどいこともあるので、気持ちを吐き出したり、今この瞬間にやっていることが大丈夫そうなのかなどを一緒に考えていくのが、この記事でも紹介されているような機関でもあると思います。
どのように関わるのがよさそうか、また、保護者の方自身の問題が何か影響を与えていそうだと思うような場合は、ぜひカウンセラーなど専門家とともに一緒に考えていくことも選択肢に入れてみてください。
参考図書
子育てのほんとうの原理原則 「もうムリ、助けて、お手上げ」をプリンシプルで解決
更新日:2025/02/04
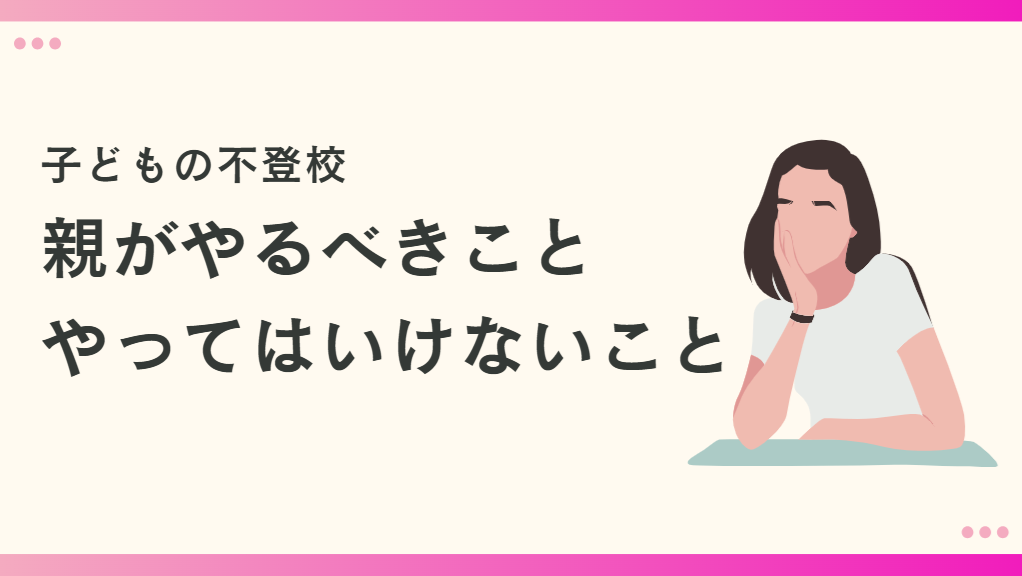

 つぶやく
つぶやく シェアする
シェアする LINEで送る
LINEで送る