・不登校の子どもが定期テストを受けたがらない。このまま放っておいて大丈夫なのか?
・定期テストを受けたがらないお子さんに保護者としてできることは何か?
・不登校中にできる定期テストの勉強は?
・小学生の不登校はテストを受けた方がよいのか知りたい
この記事を読み始めた方の中には、こんな悩みを抱えている方も多いでしょう。
保護者にとって、お子さんの不登校に関する大きな心配ごとの1つとして「無事に進学できるのか」が挙げられます。
定期テストは学校での成績に影響するため、授業はともかくテストくらいは受けた方がいいのでは、と感じる保護者も多いことでしょう。
今回の記事では、不登校でもテストを受けた方がいいのか、また不登校のお子さんがテストを受けるために保護者ができることなどを紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
そもそも不登校中に定期テストは受けられる?

まず、そもそも不登校中に定期テストは受けられるのか、お悩みの方がいらっしゃるかもしれません。その疑問にはじめにお答えします。
不登校中でも定期テストを受けることは可能
不登校中であっても定期テストを受けられるのか心配なお子さんもいるでしょうが、問題なく可能です。
不登校のお子さんの中には、学校を休んでいる間も定期テストの存在が気になっていたり、受けなければと焦ったりしているお子さんもいるかもしれません。
しかし、必ずしも学校で他の生徒たちと同じ形で定期テストを受ける必要はありません。
別室での受験や、教育支援センター、フリースクール等でテストを受けるという選択肢もあります。詳しくは、以下の「定期テストがどうしても学校で受けられない場合の対処法」の章で解説しています。
いずれの形であれ、定期テストは受けられるので安心してください。
定期テストを受けないとどうなる?

もし定期テストを受けなかった場合、お子さんの将来が心配になりますよね。特に高校受験にどう影響するかは気になるでしょう。
テストを受けないことによる影響を知っておくことは、お子さんと話し合う際の情報として重要です。ここでは定期テストを受けないとどうなるのかを、2つの項目別に紹介します。
中学校は卒業できる
結論として、中学校は定期テストを受けなくても卒業できます。
さらに言うと、入学していれば、1日も登校していなくても卒業は可能です。
中学校では、生徒の進学や卒業の裁量は、すべて校長にあります。
そのため、様々な事情があって学校にほとんど通っていないお子さんであっても、お子さんの将来のことを考えて卒業させる場合がほとんどです。
ですので、定期テストを受けなかったり、不登校であることを理由に卒業できないことはまずありません。
進学先の選択肢が少なくなる
一方、中学校は卒業できても、進学できる高校の選択肢は少なくなる可能性があります。
なぜなら、公立私立問わず、ほとんどの高校は受験の合否に学校での成績が反映されるからです。
学校での成績には、定期テストの成績以外にも、普段の生活態度や学習意欲なども含まれます。しかし不登校であれば、それらが測れず、定期テストの結果を成績に大きく反映されやすいです。
そのため定期テストを受けないでいると、成績がつかず、進学できる高校の選択肢が狭まる上に、その後の進学にも影響がでてしまう恐れがあります。
定期テストを受ける場合の4つのメリット
ここでは、不登校のお子さんが定期テストを受けない場合のメリットについて解説します。
お子さんの状況によっては、テストにこだわることなく、お子さんの心と体の健康を優先することが重要です。
テストを受けない=「学びを止める」ということではなく、お子さんの心の健康や成長に適したタイミングを見つけるための選択肢として考えてみてください。
① ストレス軽減
定期テストはお子さんにとって大きなプレッシャーです。
特に不登校のお子さんにとって、テストのプレッシャーがさらに不安やストレスを悪化させることがあります。
テストを受けないことで、そのプレッシャーから解放され、気持ちが少し楽になることがあります。
②精神的な回復に集中できる
テストを受けないことで、お子さんは学業以外の部分、特に精神的な回復に専念できるようになります。
まずはメンタルヘルスを改善し、心の安定を図ることが優先されるため、学校に戻る準備をする上での重要なステップになります。
③自分のペースで学び直せる
定期テストを受けないことで、学校の進行に無理に合わせる必要がなくなり、お子さんが自分のペースで学び直すことができます。
テストの結果を気にせず、まずは基礎的な部分や理解できていない部分を丁寧に取り組むことができるため、学びの負担が軽減されます。
④自己肯定感の低下を防ぐ
テストで良い結果が出ない場合、自己肯定感が低下することがあります。
不登校のお子さんはすでに自信を失っていることが多く、さらにテストで失敗することで自己評価が低くなる可能性があります。
敢えてテストを回避することで、そのような否定的な体験を避け、自己肯定感を維持しやすくなります。
定期テストを受けない場合の3つのデメリット

定期テストをお子さんが受けない場合、具体的にどのようなデメリットがあるのか気になりますよね。ここでは、定期テストを受けない場合のデメリットを3つ具体的に紹介します。
①受験に悪影響をおよぼす恐れ
上の項目でも紹介しましたが、定期テストを受けないと学校での成績が下がるため、受験の合否判定の際に不利になってしまいます。そうなると、進学できる高校の選択肢は少なくなってしまいます。
そのため不登校のお子さんであっても、定期テストに向けて勉強をし、実際にテストを受けて学校での成績を上げておくことが望ましいでしょう。
②自分の学力を把握できない
定期テストを受けないでいると、お子さんの学力を把握できません。そうなるとお子さんの進学先を決める際になんの証拠もないので、途方に暮れてしまうでしょう。
お子さんの学力レベルは、進学先の高校を選ぶ上での道標になるとても大事な情報です。
また定期テストを受けることで、お子さんの学力レベルのみならず、得意科目や苦手科目、不足している知識や能力など、将来を考える上で役立つさまざまな情報が得られます。
ですので、定期テストを受けないことは、お子さんの将来を考える上で良くはないかもしれません。
③勉強のモチベーションが下がる
定期テストを受けることは、勉強を進める上での大きなモチベーションになります。
不登校のお子さんの中には勉強嫌いのお子さんも多いでしょうが、勉強が嫌いでもどうにか勉強するきっかけとして、定期テストは役に立ちます。
集団内での順位が明確になることで、もっと順位を上げたいという勉強のモチベーションにつながる場合が多いです。目の前に目標があると、なんとか頑張ってみようという気力も湧いてきやすいです。
そのため、定期テストを受けないでいると、勉強の目的やモチベーションを見出せず、より勉強しなくなる原因になります。
そうなると周囲との学力の差はより広がっていき、なおさらお子さんは定期テストを受けたくなくなるかもしれません。
不登校のお子さんが定期テストを受けるために保護者ができること

ここまで、定期テストを受けないことのデメリットなどを紹介しました。
お子さんの将来を考えても、やはりお子さんにはどうにかして定期テストを受けてほしいですよね。
ここでは、定期テストを受けたがらない不登校のお子さんに対して保護者ができることを4つに分けて紹介していきます。
①お子さんがテストを受けたがらない理由を聞く
保護者がいくらお子さんの将来を思ってテストを受けてほしいと言っても、お子さんにはお子さんなりの言い分があるはずです。お子さんにとってみても、テストを受けた方がいいのは分かりきったことでしょう。
お子さん自らテストを受けようという気にさせるためにも、お子さんの「テストを受けたくない」という気持ちに寄り添ってあげることが大切です。
以下はお子さんがテストを受けたくない理由の例です。
- テストを受けたところでどうせ良い点は取れないし、周りの同級生にそれを知られたくない
- テストだけ受けにきたと思われそうで嫌
- そもそもテストを受けるために学校に行って、周りの同級生や先生に会いたくない
保護者にとってみれば、お子さんの将来の不安に比べれば些細な問題に感じるかもしれませんが、お子さんにとってはこれらは大きな問題です。
上の例の場合、お子さんがテストを受けたくない大きな理由は「周りの目」にあります。そのため学校と相談して、テストを別室で受けたり、他の生徒たちとタイミングをずらせないか相談してみることが有効です。
お子さんの理由をしっかりと受け止め、これからどうしていきたいかをお子さんとじっくり考える必要があります。
②「別室」「別日」などテストの受け方を学校に相談する
お子さんがテストを受けたくない理由の例でも紹介したように、テストを受けたくない理由が「周りの目」にあることは少なくありません。
もし、お子さんが周りの目を気にしているようであれば、学校に相談して、テストを別室で受けたり、他の生徒たちとタイミングをずらして別日で受けられないか相談してみることが有効です。
③お子さんが主体的になるまで辛抱強く待つ
保護者として、お子さんが定期テストを受けたがらないことを不安に思うのは当然です。
しかし、だからといってその気持ちをお子さんに押し付けるのは危険です。
不登校のうえ、反抗期を迎えたお子さんに勉強やテストを無理強いするのは逆効果です。
あくまでテストを受けるか受けないかはお子さんの課題です。
保護者の不安解消のためにお子さんがテストを受けるのではありません。
そのため保護者としてできることは、お子さんになんとかテストを受けさせようとあがくのではなく、お子さんから助けを求められた時に全力でサポートしてあげることです。
それまではお子さんを信じ、辛抱強く待つことが大切です。
④学校の先生と積極的にコミュニケーションをとっておく
お子さんが不登校で学校に通っていなくても、学校の先生とは積極的にコミュニケーションをとっておきましょう。
学校は様々な事情で学校に通いたくないお子さん、テストを受けたくないお子さんに対して様々な対処法を提案してくれます。
お子さんがどうしても定期テストを受けたくないのなら、それに代わる代替案を示してくれる場合もあります。
またお子さんが不登校であっても、保護者が学校から課題のプリントを受け取って、それを学校に提出することでも成績アップにつながります。
ですので、お子さんの問題を保護者一人で抱え込むのではなく、積極的に学校を頼ってみるのもおすすめです。
不登校中にできる定期テストの勉強は?

不登校のお子さんが定期テストを受けることに決めた際、どのように勉強をしていくのがよいか、お悩みの方も多いことでしょう。
勉強の仕方としては大きく分けて、自主学習と外部サービスを利用することが挙げられます。ここではそれぞれの定期テストの勉強法を4つに分けて紹介します。
①毎日の勉強習慣をつくる
不登校のお子さんがいきなり定期テストに向けて勉強しようとしても、勉強習慣が身についていない場合、勉強自体に大きなハードルを感じてしまいます。
特に不登校で授業さえ受けていないお子さんにとっては、テストを受けるだけでも大きな負担になるので、そのための勉強も同じように負担になるでしょう。
そのため、最初の頃は毎日数分だけでもいいので、机に向かって勉強する習慣をつけることをおすすめします。
その習慣を継続できると、徐々に勉強する抵抗が薄れていき、テスト勉強へのハードルも下がっていくことでしょう。
保護者としては、お子さんが挫折しないように、適度に励ましつつ見守ってあげることが大事です。
②科目を絞ってテスト勉強をする
定期テストを受けるとなると、全科目受けなければならないと思いがちですが、実際は必ずしも全て受ける必要はありません。
お子さんがテストや、テストに向けての勉強に大きなハードルを感じているなら、思い切って、お子さんの得意な科目や好きな科目に絞って勉強することをおすすめします。
そうすることで、もしお子さんの得意な科目のテストで良い点数が取れれば自信につながり、次のテストや勉強に対してより意欲的になるかもしれません。
また、科目数を絞ったとしても、実際にテストを受ける経験が積めるので、テスト勉強をしてテストを受ける流れや、テストの場の雰囲気もわかります。
ですので、はじめはスモールステップでもいいので、一歩前進することが大切です。
③簡単な学習計画を立て自主学習する
不登校のお子さんにとって、長い間慣れないテスト勉強を続けるのはとても難しいです。
そのため、簡単にでもいいのでテスト当日までの学習計画を立てましょう。
しかし、学習計画を立ててそれ通りに勉強するというのは、お子さん1人では困難です。
そこで、保護者のサポートが大事になってきます。
テストに向けて、「この日はこの科目をここまで勉強しよう」といったようなスケジュールをお子さんと一緒に組んでみましょう。
不登校のお子さんにとって、計画によって自分の勉強を厳しく管理されるのは辛いものです。
ですので、きちんと休憩時間も十分に確保し、初めは無理のない余裕ある計画を立てましょう。
④家庭教師やオンライン学習サービスを利用する
お子さんの自主学習や、保護者のサポートだけでは限界があると感じた際には、家庭教師やその他オンラインサービスを利用することも一つの手です。
家庭教師やオンラインサービスを利用する場合、自宅で勉強を続けられる分、慣れ親しんだ居場所で安心して勉強ができます。
家庭教師を利用して保護者と家庭教師で協力しながら学習計画を立て、二人三脚でフォローアップ体制をつくるのもいいでしょう。
家族以外の人と関わりを持つことは良い刺激になって、お子さんの心にとってもプラスにつながる可能性もあります。
家庭教師やオンライン学習サービスは豊富に存在するので、お子さんにあったサービスがないかWebで調べてみてください。
お子さんが中学生であれば、出席扱いと認められるオンラインのフリースクール等もおすすめです。
定期テストがどうしても学校で受けられない場合の対処法

どうしてもお子さんが学校で定期テストを受けられないという場合には、学校以外の場所に相談してみるのも1つの選択肢です。
不登校のお子さんの中には、教室に入っただけで体調を崩してしまう人もいるでしょう。
定期テストを受けるためにわざわざ無理して教室に入る必要はありません。
ここではどうしても学校で定期テストが受けられない場合の対処法の例を紹介します。
◆オンラインでテストが受けられないか学校と相談する
最近はオンラインを用いた授業やテストが普及しています。
ですので、学校側がオンライン試験のシステムを導入している場合、学校に行かず遠隔でテストを受けられます。
一度学校側に問い合わせてみると良いでしょう。
オンラインでのテストができないのであれば、別室での受験や、他の生徒がいない時間帯にテストが受けられないか先生と相談してみてもいいかもしれません。
お子さんがどんな環境ならテストを受けられるのかのヒアリングもかかさず行いましょう。
◆教育支援センター等の学習支援機関を利用する
教育支援センター(適応指導教室)とは、不登校のお子さんに対するカウンセリングや学習指導、体験学習のサポートなどを行っている公的機関です。各都道府県・市町村に1,634カ所設置されています。
他にも、「児童相談所」「精神保健福祉センター」など、さまざまな公的機関があります。
教育支援センターについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
▶教育支援センター(適応指導教室)ってどんなところ?!目的やできること、フリースクールとの違いを徹底解説!
教育支援センターでは、個別指導や特別テストなどを実施しているところがあります。
テストの成績が学校の成績に反映されるとは限りませんが、テストを受けることで自分の実力や学習の課題を知ることができるので、活用してみるのも選択肢の1つです。
◆フリースクール等の民間の施設に通う
フリースクールなどの民間施設を利用するのもおすすめです。
フリースクールとは、なんらかの事情で学校に通うことが難しいお子さんに、学校に変わる「第二の居場所」を提供している施設です。
フリースクールの他にも、オルタナティブスクールやホームスクールなどがあります。
フリースクールについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
▶フリースクールとは?基本情報から学費・進学可否まで幅広く解説
フリースクールなら、お子さんに合った自由度の高いプログラムで学習できるほか、似た境遇の仲間と規則正しい生活をすることになり、学校復帰のための大きな一歩になります。
フリースクールに通うと学校の出席扱いになるようなサポート体制が整っている場所もあります。
学校の定期テストをフリースクールで受けられる場合もありますので、一度調べてみると良いでしょう。
オンラインのフリースクールなら『SHINGAKU』
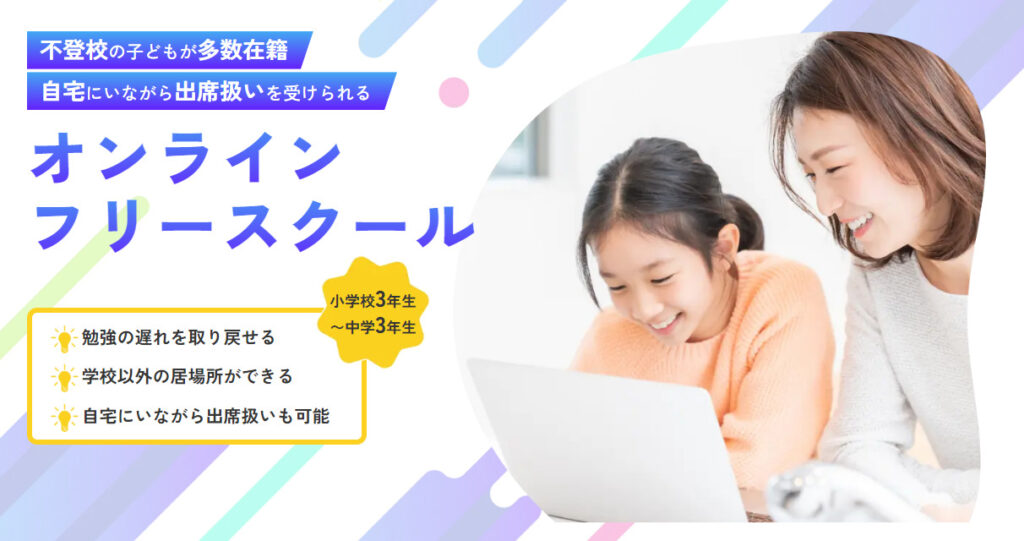
お子さんの希望や通学の事情により、オンラインでの学習を希望する場合はオンラインフリースクールがおすすめです。
SHINGAKUでは、自宅にいながら楽しく学習やコミュニケーションを取ることができます。また、出席扱い制度の申請サポートも対応しているため、内申点などに不安がある方には心強いのではないでしょうか。
関西で60年の歴史ある成基コミュニティグループが運営母体ですので、安心してご利用いただけます。
興味のある方は、ぜひこちらのページをご覧ください。
▶【小学3年生~中学3年生対象】オンラインフリースクール「SHINGAKU」
小学生の不登校はテストを受けることはできる?
小学生の不登校のお子さんも、テストを受けることは可能です。
学校に行くことや教室に入ることに抵抗感があるお子さんでも、テストを受けられる方法はいろいろあります。
ただし、各学校や教育委員会によって対応が異なるため、学校と相談しながら調整する必要があります。
別室でのテスト受験
不登校のお子さんが教室に行くのが難しい場合、学校内の別室で個別にテストを受けることができる場合があります。
通常の教室でのプレッシャーを避け、静かな環境で集中して受けられるように配慮されます。
自宅でのテスト受験
テスト問題を自宅で受験する選択肢もあります。
この場合、保護者が監督者としてテストの進行を見守り、学校にテストを提出する形式になります。
後日受験の調整
テスト当日に体調が整わない場合、後日テストを受けるための調整を学校と行うこともできます。この方法では、お子さんの状態に合わせて無理のない時期に受験できるようにすることが可能です。
オンライン受験
一部の学校では、オンラインでのテスト受験が可能なシステムを導入している場合があります。これにより、お子さんは自宅からインターネットを通じてテストを受けることができ、学校に行かずとも学力評価を受けられます。
小学生の不登校はテストを受けるべき?
ここでは、小学生の不登校のお子さんがテストを受けるメリットを解説します。
ただし、気をつけていただきたいのは、テストを受けることにメリットはありますが、無理をさせないことが最も大切です。
お子さんの状態を観察し、コミュニケーションをとって、心身の健康の回復を優先させるべき時期かどうかを見てあげてください。
また、テストを受けなくても小学校を卒業することは可能ですので、プレッシャーをかけずに子どものペースを大切にしましょう。
学習進度の確認
テストは、お子さんが学んだ内容をどれくらい理解しているかを確認する機会です。学習の進度を確認することで、どの部分にサポートが必要かを把握できます。
学校復帰への準備
テストを受けることで、学習に対する自信がつく場合があります。学校に戻る準備として、段階的に学習に慣れることが期待できます。
達成感の提供
小さな成功体験を積むことで、達成感を得ることができ、不登校の克服につながることもあります。テストの結果が必ずしも良くなくても、挑戦することで自己肯定感を高めることができます。
今後の進路への準備
高学年になると、進学に向けた準備も考慮する必要が出てきます。テストを受けることで、進路選択や進学に関する情報が得られる可能性があります。
【まとめ】

不登校のお子さんが定期テストを受けたがらないのは不思議なことではありません。
当たり前のように定期テストに臨んできた保護者の方であれば、定期テストを受けたがらないお子さんに対し、将来の不安を感じて焦ってしまいがちですが、そうした気持ちを押し付けてしまうと逆効果です。
お子さん、学校双方とのコミュニケーションを欠かさず、お子さんがテストを受けたがらない理由に応じて、保護者としてできるサポートを考えましょう。
また、学校やその他の外部機関を積極的に活用しながら、お子さんが主体的に定期テストを受けようと思えるようになるまで、辛抱強くサポートをし続けましょう。
更新日:2024/12/04




 つぶやく
つぶやく シェアする
シェアする LINEで送る
LINEで送る











